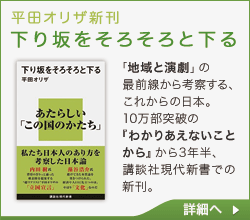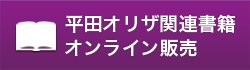『もう風も吹かない』の初日が近づいてまいりました。
今日は「小屋入り」、要するに舞台美術を仕込む日でした。私は朝から新幹線で盛岡へ。
お昼は久しぶりに、盛岡劇場の新沼さん、架空の劇団のくらもちさんと食事をしながら、被災地の状況など伺い、盛岡での来年度の事業について相談をしました。
午後からは、岩手県歯科医師会の講演会でした。何で呼ばれたのか自分でもよく分かっていませんが、お土産に歯ブラシをいただきました。
明日は午前中、東京藝大で会議、そして午後から舞台稽古。明後日ゲネプロ、そして木曜日に初日です。
おそらく当日券も出ますし、二週目はまだ売り止めの日はありません。ただ、やはり追加公演がお薦めとのことです。よろしくお願いします。
追加公演が先に来るように、サイトを書き換えてもらいました。
https://komaba-agora.com/ticketsell/
http://s.seinendan.org/play/2013/08/1822
1月の伊丹公演も、早々と発売を開始したのですが、こちらは内田樹先生にアフタートークに来ていただく回のみ、すでに売り切れ間近のようです。ありがたいことです。
さて、当日パンフレットにも入れてあるのですが、十年前、このお芝居の初演の際に書いた文章を、ここに載せておきます。いま読み返すと、気恥ずかしいくらいに熱い文章ですね。当時、私は熱血教員でした。その後、桜美林を辞めるに至った経緯は、今回の吉祥寺での公演の当日パンフレットの方に書いてあります。
このお芝居では、日本が通貨危機に陥り海外援助がすべて停止となり、青年海外協力隊も募集停止が決まるという設定になっています。十年前に書いた作品ですが、その可能性は、十年前より増していると思われます。今回、再演にあたって、書き直さなければならない部分は、ほとんどありませんでした。
ぜひ、劇場に足をお運びいただければと存じます。
『もう風も吹かない』初演時当日パンフレット原稿
この『もう風も吹かない』という作品は、二年半ほど前に着想を得て、その時点で全体の構想を当時の最高学年である二年生たちに話した。「卒業公演に相応しくない、夢も希望もない作品を書いてやる」と言って、そしてまさにいま、その通りになった。
そのころ私は、青年海外協力隊の制度改革のための諮問委員のような仕事をしていて、二本松や駒ヶ根の国内訓練所、はたまたモロッコまで行って、現地の協力隊の活動ぶりなどを視察させてもらっていた。特に訓練所の様子というのが劇作家としての興味をひき、これは芝居になるなと瞬時に思った。二十歳から三十九歳までの男女が、三ヶ月という中途半端な期間、世間から隔離されるようにして訓練を受ける。そして、その人々はすべて、三ヶ月後には途上国に赴き、過酷な生活を強いられる。これほど劇的で濃密な空間と時間は、いまの日本には、そうはないだろう。
諮問委員会の席上、「私はいずれ、この訓練所の風景を芝居にしたいと思う。そしてそのとき、JICAの人々は、私を委員にしたことを強く後悔するだろう」と述べた。そしてまさにいま、その通りになった。
2000年4月、既存の体育館の片隅に急ごしらえで作った小さなスタジオで、桜美林大学文学部総合文化学科演劇コースは、その産声を上げた。
「地域の演劇活動の中核を担える人材を育成する」という理念のもと、希望に満ちた学生たちと、この理念に共鳴してくれた演劇人たちが、小さなスタジオに集まってきた。
私自身は、この演劇コースを開設するにあたって、先の大きな理念以外に、コース運営の方針として二つの事柄を考えていた。
一つは、この大学では、「演劇とはかのようなものである」という一つの定見を示すのではなく、「演劇とは、どのようなものであるか?」という永遠の疑問符を、共に持ち続け考え続けられるようなプログラムを作ろうということ。より具体的には、一つの演劇作法に囚われるのではなく、様々な一線の演出家から直接指導を受け、学生が四年間のうちに自分のやりたい演劇の方向性を見定められることを目標に定めた。私は毎年、最初の授業で、一年生たちに次のような説明をする。
「演出家というのは、何らかの欠落を持った、歪んだ人々です。できるだけ多くの不思議な演出家と出会って、君たちがかろうじてつき合っていける人を見つけてほしい」
学生たちは、ここまで、よく私の欠落を補ってくれたと思う。
もう一点は、スタジオ、劇場の運営を、できる限り学生に任せたいと考えた。これは、大学側の管理体制と抵触する部分も多く、混乱、衝突の連続だった。この四年間の経験を通じて、学生たちは、権利とは闘い獲得するものだということを、深く強く心に刻んだはずだ。それは、学科創設初期の学生だけが得られる特権的な体験だった。
01年には百人ほどが入る小劇場ができ、この年からOPAP(桜美林パフォーミングアーツプログラム)が始まった。
他大学の演劇科が、多くの場合、学年ごとの成果発表会を行うのに対して、OPAPの特徴は、学年を越えて全学でオーディションを行い、その時点で考えられるベストのメンバーで公演に臨む点にある。一年次からずっとOPAPに出演している学生もいれば、毎回オーディションに落ちてしまう学生もいる。厳しいようだが、実際の演劇界では、これはごく普通のことなのだから、学生にもその厳しさに慣れておいてもらわなくては困る。私の調べた範囲では、欧米の多くの大学の演劇科も、似たような制度で運営されている。
小劇場ができ、学生たちの自主的な公演も活発になってきた。桜美林出身の劇作家や演出家が、演劇界で活躍する日も近いだろう。OPAPも、いずれ学生のオリジナル作品をやれるようになれればと思っている。
そして、今年四月、淵野辺駅前に待望の本格的な劇場空間プルヌスホールがオープンした。最先端の機能をシンプルに折り込んで作られたこの劇場は、二百人規模のホールとしては、首都圏でもっとも使いやすく、美しい空間になったと自負している。またこの劇場は、地域社会に開かれた劇場として位置づけられており、この秋からは、相模原市と連携した市民向けのワークショップなども開催される。学生主催のワークショップも同時に開かれていて、朝比奈尚行さん、ケラリーノ・サンドロヴィッチさんはじめ、数多くの学外の演劇人もここを訪れている。
学生たちの献身的な努力と、いくつかの幸運や強運が重なって、私たちはいま、この『もう風も吹かない』を創るに至った。たったの四年間で、ここまでのことを成し遂げたのは、ある種の奇跡に違いない。当然、はじめての卒業生を送り出すにあたって、それなりの感慨もある。
だがしかし、「たったの四年間で」ということは、いまを生きる学生たちには、何の関係もないことで、一期生、二期生にしてみれば、どうして自分たちだけが、こんな苦労をしなければならなかったのだろうと思っているかもしれない。私もそれを、申し訳ないことだと思っているが、十年、二十年後に、少しでもそれが、良い方の思い出として心に甦ってくれることを祈るしかない。
私は、ここ十年ほど、日本は滅びるという妄想に取り憑かれ、そのような作品ばかりを多く書いている。海外での仕事が増えるにつれ、この妄想は、ほとんど確信へとかわり、今年は、『南島俘虜記』『もう風も吹かない』と、共に、行き場のない日本を描く作品を書くに至った。
学生には授業でも言い続けてきたことだが、この滅びの時にあたって、私たちが考えなければならないことが二つある。
一つは、先回の大日本帝国の滅亡の時のように他国に迷惑をかけることなく、どうにか潔く滅びることはできないものかということ。このことは、珍しく、今回の戯曲の中にも台詞として書いた。
もう一つは、たとえ日本国が滅びても、私たち一人ひとりも、その一人ひとりが形成する地域の文化も、国家の巻き添えになって滅びる必要は露ほどもないということだ。
経済と物質を唯一至上の価値とするようなこの国は滅びてしまってかまわない。人の心を一つの型に押し込み、そこから外れたものを汚物のように忌み嫌うような社会は、滅びてしまってかまわない。
演劇を作るという行為を通じて、個々人が自分の頭と心と身体で、何かを感じ取り、考え続けること。そして、そこから得た結果を自分の判断として、責任を持って他者に向かって表現していくこと。その表現の孤独に耐えること。私が大学で教えられることがあるとすれば、たぶん、そんなことくらいだろう。
いま、バブル後の焼け跡に、そこが焼け跡だということさえ知らず、学生たちは立っている。復興の槌音は、遠くにも聞こえない。黒い雨も、核戦争後に降るという灰色の雪も降ってはこない。砂漠を吹き抜けるはずの風さえも、この荒野には吹かない。彼らは、彼女らは、この見えない廃墟に、いつまでも、いつまでも静かに立ち尽くさなくてはならない。
だが、その立ち尽くす力にこそ、私は賭けたいと思う。呆然と立ち尽くす彼ら、彼女らの視線の向こうに見えているものを、私も見たいと思う。その一点に賭けて、君たちと作品を創っていきたいと思う。
2003年11月 平田オリザ
*この戯曲は、近未来の、架空の訓練所を想定したフィクションである。たとえば、ルアンダに行く俳句隊員は現存しない。念のため。