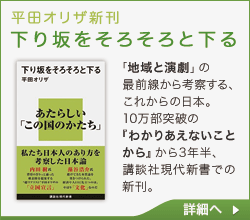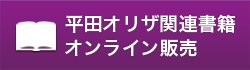いよいよ今日は『幕が上がる』の初日です。日によっては、少しずつキャンセル待ちの当日券も出るようです。
なお、舞台版『幕が上がる』の上演台本は、文藝別冊「平田オリザ」に掲載予定です。発売は5月22日(金)の予定。
http://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309978598/
いつの間にか、こんな記事も出ていました。
ドイツ語なので、一文も分かりませんが、自分が何か関わっていることは分かる。
チケットも売り出されたようです。来年1月の舞台ですが。
福島の哀しみを描いたオペラです。こちらも文藝別冊に掲載予定。
『冒険王』の稽古はこれから佳境です。『新・冒険王』は城崎に行って集中して作るので、まず『冒険王』の方を、軽く通せる程度まで仕上げます。
http://www.seinendan.org/play/2015/03/4357
こちら、絶賛発売中です。舞台版『幕が上がる』をご覧になった方で、少しでも舞台に関心を持たれた方は、ぜひ観に来てください。本場の同時多発をお目にかけます。
その前に、こちらの公演もあります。仏人俳優たちは、明日来日予定です。
http://www.seinendan.org/play/2015/03/4316
こちらも前売りは完売。日によって当日券が出ます。
なんだか忙しいなぁ。
これから一週間は、小竹向原(『冒険王』稽古場)と早稲田(アンドロイド版『変身』上演)と、六本木(『幕が上がる』上演)を回遊する日々です。
日記の続き
4月15日(水) 朝6時に家を出て、初めて品川発で福島県いわき市へ。出迎えの車で双葉郡広野町へ。10時前に、ふたば未来学園到着。
生徒たちは、1、2限に『幕が上がる』を鑑賞。3,4限から、1クラスずつワークショップ。4クラスあるので、今日は昼食を挟んで2クラス。生徒たちは楽しんでくれたようです。学食での昼食の時間には、いろいろ質問もされました。
終了後、先生方と打ち合わせ。
ふたば未来学園のことは、講談社の「本」の連載に書きました。ふたば未来学園に対して批判的な方に対する私の見解も、そちらに書きました。もうすぐ発行なので、ご覧下さい。
いわきまで車で送っていただき、17時台のJRで帰京。もう、戯曲の執筆。締め切りまであと5日。台湾で出版される『演劇入門』の前書きを執筆、送付。台湾では『幕が上がる』の翻訳出版も検討してくれているらしい。
以下、連載原稿から演劇に関係するところを一部抜粋。
東北発未来塾の学生にも、ふたば未来学園の生徒たちにも、対話劇を創るというワークショップを進めてきた。
どちらも簡単な演劇のワークショップを受けてもらってから、被災地に取材に出かけて、それを題材に劇を創る。まず彼らにお願いしたのは、以下のような事柄だ。
私は「対話劇」を、一つの主義主張を伝えるのではなく、異なる価値観や意見を持った人々が登場し、戸惑ったり、理解し合ったりしながら対話を進めていく演劇のスタイルと定義している。だから、ここでは、「復興が進んでいる」とか「希望が見えてきた」とか、まして「絆」だとか「思いやり」だとか、そんなものは描かなくていい。
復興は進んでいないのだ。
なぜ、復興が進まないのかという現実をまず直視しよう。多くの人々が、善意で復興に取り組んでいるにも関わらず、それが進まないのはなぜなのかを考えよう。その時に大事なのは、誰かを悪者にするのではなく、一人ひとりの善意を信じながらも、遅々として進まない復興の難しさを描くことだ。
東北発未来塾のある班は、いわき市内の仮説商店街を取材した。現在、仮説商店街は賑わっているのだが、数年後には、市が建てる大規模商業施設に移転しなければならない。移転後は家賃も支払わなければならないことから、廃業を決めた店舗も多い。ここで行政の一方的な措置を批難するのはたやすい。しかし、この大規模商業施設の建設を進めているのも、いわき市民なのだ。将来の被災地の発展を考えるなら、集客力のある施設を作った方がいい、それなら若者も戻ってくると言う考えにも一理ある。
実際、この班も、当初は、東京から来た開発業者を悪者にすることで話を進めようとしていた。しかし、それではリアリティに欠けるという私の指摘を受け、その業者もまた、若者が集まるようなおしゃれな施設を真摯に作ろうとしているという設定となった。だが、その善意もまた、古くからの商店街になじんだ人々にとっては徒となる。